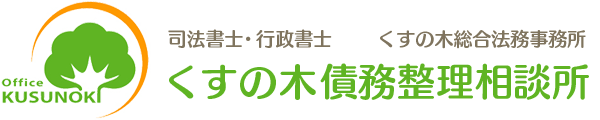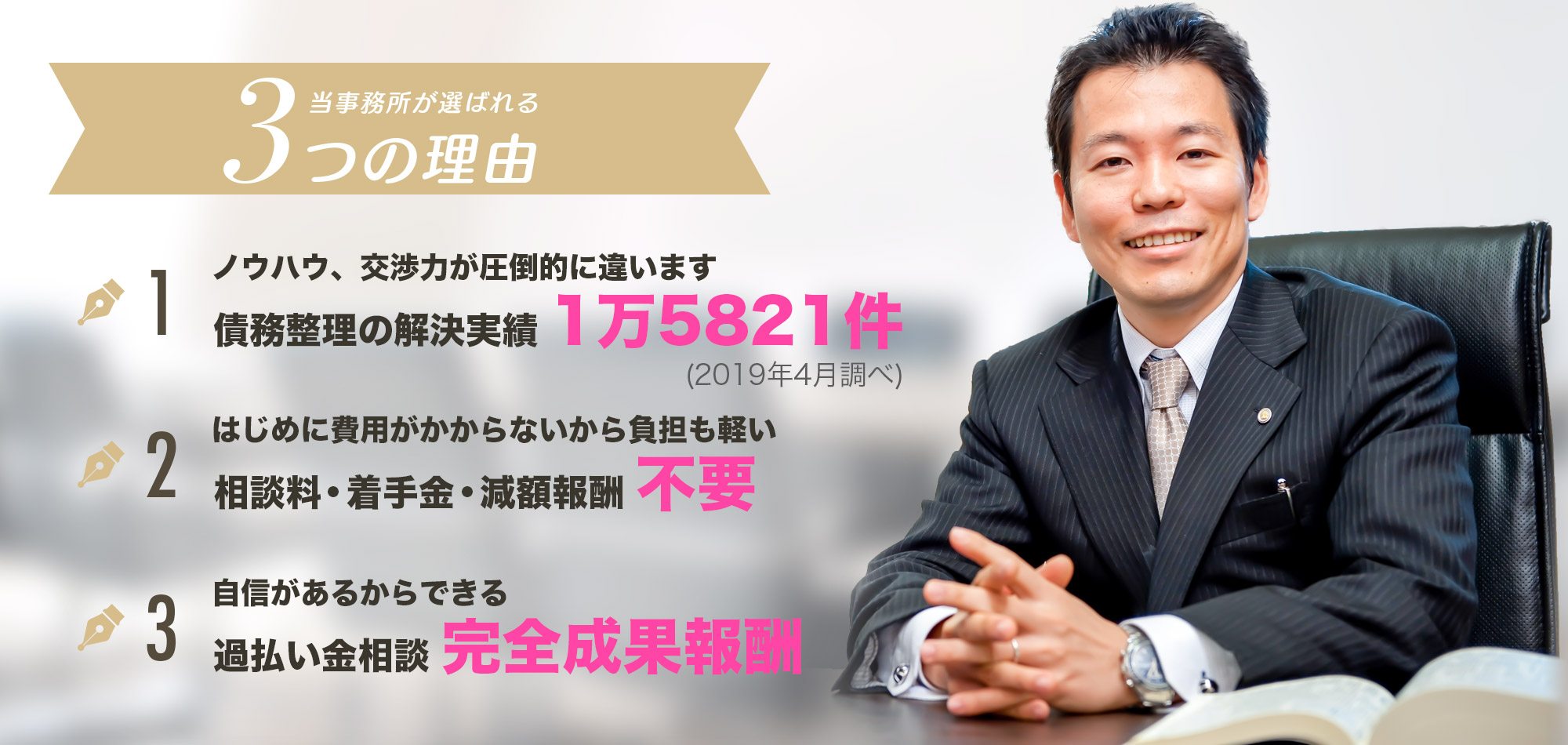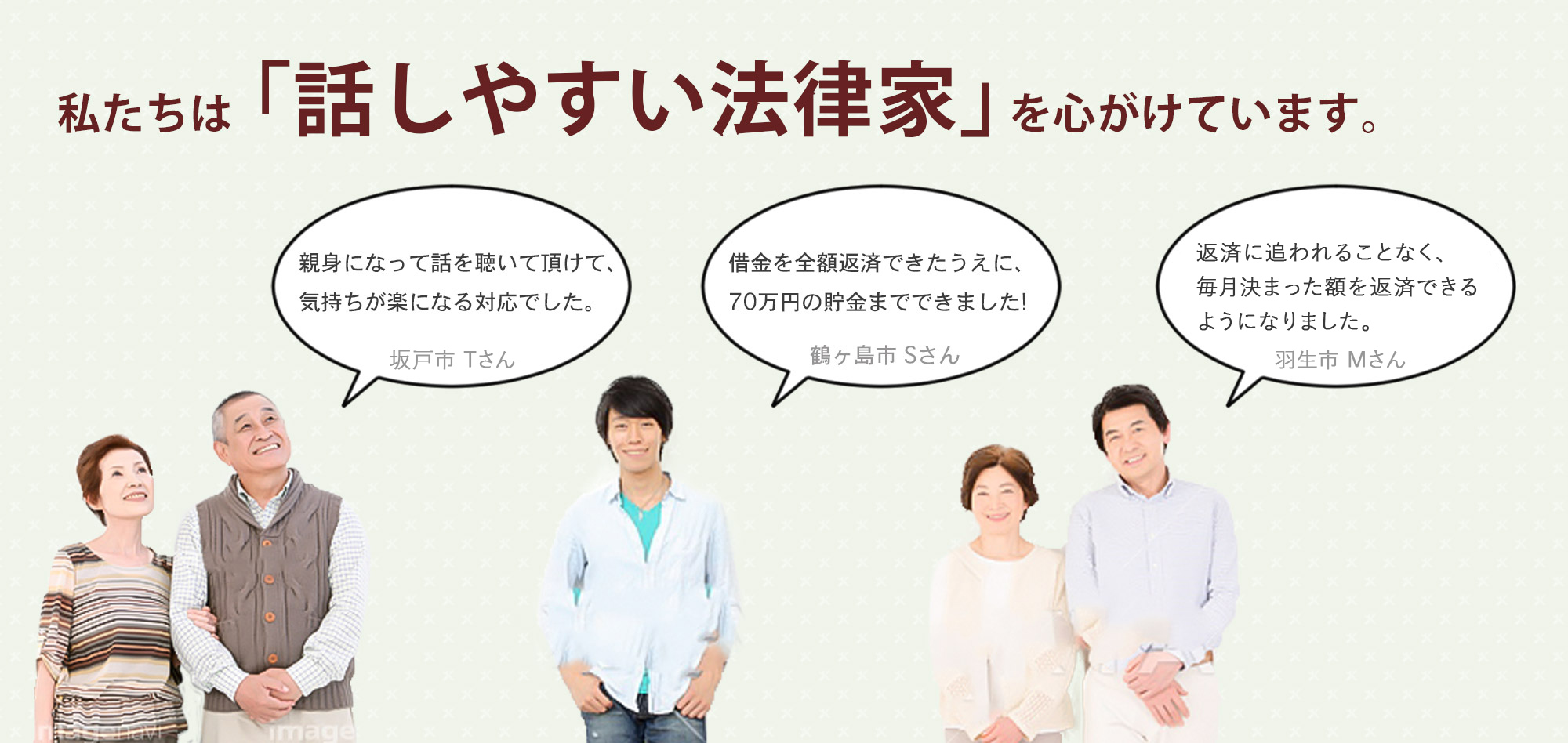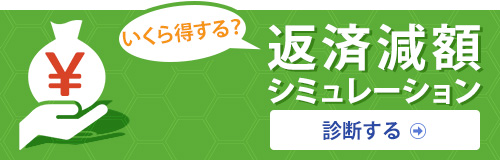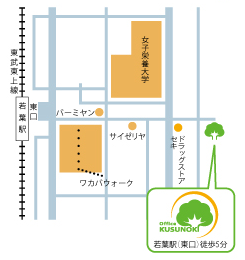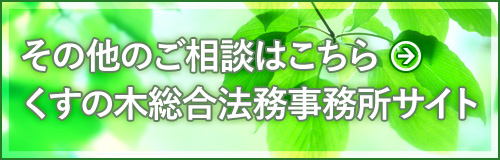Last Updated on 2025年9月28日 by 監修者:司法書士 藤田太
借金に悩み、給与や銀行口座、自宅などの財産の差し押さえの通知を手にして、不安で眠れない夜を過ごしているかもしれません。「もう手遅れかもしれない」と、絶望的な気持ちになるのも、無理もないでしょう。しかし、差し押さえの段階によっては、適切に対処することで差し押さえを回避できる可能性もあります。
この記事では、「差し押さえ」とは何か、その仕組みと回避する方法について解説します。
差し押さえとは何か?基本の知識と任意整理への影響
「差し押さえ」——聞くだけで不安になることだと思います。差し押さえとは、裁判所の手続を通じて給与・預金・動産などの財産を強制的に確保する措置です。まずは、差し押さえの仕組みを詳しく解説していきます。
差し押さえとは何か?仕組みと法的根拠
差し押さえとは、借金の返済が滞った際、債権者が裁判所を通してあなたの財産を強制的に回収する法的手続きです。これは民事執行法という法律に基づいて行われます。まず貸金業者などの債権者は、『債務名義』と呼ばれる裁判所の判決や支払督促など、「強制的に財産を差し押さえてもよい」という公的な許可を取得します。その後に、この差し押さえが実行されるのです。
この制度は、債権者の権利を守るために設けられたものです。もし債務者が自ら返済に応じない場合、これが最終的な手段となります。差し押さえが実行されれば、あなたは対象となった財産を自由に扱えません。最終的には、その財産が売却され、債権者への返済に充てられることとなるでしょう。
ただし、重要なのは、差し押さえが債権者の一方的な判断だけで実行されることはないことです。必ず裁判所での手続きが必要であり、あなたにも一定の権利が保障されています。例えば、生活に最低限必要な財産は差し押さえが禁止されており、給与についても全額が対象となるわけではありません。
差し押さえの対象となる財産一覧|給料・預金・不動産・車
差し押さえの対象となる財産は、あなたの生活が完全に立ち行かなくなることのないよう、法律で詳細に定められています。
給与・賞与について
最もよくある差し押さえが給与差し押さえです。しかし、手取り額の4分の1までが上限と定められています。また、手取り月収が44万円以下の場合は、33万円を超える部分のみが対象となります。例えば、手取り月収25万円の方であれば、差し押さえられるのは約6万2,500円にとどまり、残りの約18万7,500円は生活費として確保される計算です。
預金・現金について
銀行預金は差し押さえの対象となります。ただし、現金については99万円以下は差し押さえ禁止財産とされていますのでご安心ください。しかし、預金口座に入っている現金は「預金債権」として扱われるため、この保護の対象外となる点には注意が必要です。
不動産・自動車について
自宅や土地などの不動産も差し押さえの対象となり、最終的には競売にかけられる可能性を否定できません。自動車についても原則として差し押さえの対象ですが、仕事で使う営業車や、価値が20万円以下の車両は処分の対象とはならず、手元に残せる場合もあります。
差し押さえが実行される条件とタイミング
差し押さえが実行されるまでには、いくつかの段階があります。債権者がいきなりあなたの財産を差し押さえることはできません。必ず、次のような法的な手続きを踏む必要があるのです。
第一段階:債務名義の取得
債権者はまず、裁判所に訴訟を起こすか、支払督促の申立てを行います。支払督促の場合、あなたが2週間以内に異議を申し立てなければ、「債務名義」が成立します。これは、裁判所の確定判決と同じ強い効力を持つもので、この時点で法的には差し押さえの準備が整ったことになります。
第二段階:強制執行の申立て
債務名義を取得した債権者は、裁判所に対し、強制執行の申立てを行います。この際、差し押さえる財産を具体的に特定しなければなりません。給与差し押さえの場合は勤務先を、預金差し押さえの場合は金融機関名と支店名を明確に記す必要があります。
第三段階:差し押さえの実行
裁判所が強制執行を認めると、あなたの勤務先や金融機関に差し押さえ命令が送達されます。この通知が届いた時点で差し押さえが確定し、給与であれば翌月分から、預金であれば即座に実行されることになります。
最初の督促状が届いてから実際に差し押さえが実行されるまで、早ければ3〜4ヶ月程度で進むケースもあります。特に、督促を無視し続けていると、手続きがより迅速に進んでしまう傾向があるため注意が必要です。
任意整理の仕組みと差し押さえへの効力
任意整理は、裁判所を通さず、あなたと債権者が直接話し合い、借金の返済条件を見直す債務整理の方法です。主に利息のカットや、分割払いの期間延長を交渉することで、月々の返済負担を軽くしていくことが可能となります。
差し押さえ前の任意整理の効果
もし差し押さえが実行される前に任意整理の手続きを始められれば、多くの債権者は差し押さえを停止したり、一旦見合わせたりしてくれる可能性が高いです。これは、任意整理によって確実に借金を回収できる見込みが立てば、裁判や強制執行にかかるコストや手間を避けたいと考える債権者側の合理的な判断といえるでしょう。
司法書士や弁護士が債権者に対し、任意整理の依頼を受けたことを知らせる受任通知を送付すると、貸金業法に基づき債権者からの直接的な取り立ては停止されます。この効果により、差し押さえの準備も一時的に中断されることが多く、交渉のための貴重な時間を確保することができます。
差し押さえ後の任意整理への影響
一度差し押さえが実行されてしまうと、任意整理による問題解決は非常に難しくなります。差し押さえられた給与や預金を元に戻すことは原則としてできません。債権者側も、強制執行で確実に回収できる状況では、任意整理の交渉に応じるメリットが少なくなってしまうからです。
ただし、差し押さえが実行された後でも、残った債務については任意整理の対象となる可能性があります。例えば、給与差し押さえで一部の借金が回収されても、全額が清算されたわけではない場合、残りの部分について任意整理を検討することは可能です。
差し押さえを回避するには、対応のタイミングが極めて重要です。督促状が届いた段階、あるいは裁判所から支払督促が送達された段階など、それぞれの状況で最適な対処法が異なります。早急に司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
通知段階別の緊急対応マニュアル
債権回収の法的手続きには、その段階が明確に定められています。それぞれの段階には対応期限があり、それに応じた有効な対処法が存在するのです。今、最も重要なのは、あなたが受け取った通知の種類を正確に把握し、残された時間の中で最も効果的な行動を取ることでしょう。ここでは、代表的な3つの通知段階における具体的な対応方法を詳しくご説明します。
【支払督促】異議申立ての14日ルール|具体的手続きと書類作成
支払督促とは、債権者が簡易裁判所に申し立てることで発行される、比較的簡易な手続きです。この通知を受け取ったあなたは、『14日以内』という厳格な期限内に異議申立てを行う権利があります。
異議申立てとは
異議申立てとは、債権者の主張(借金の請求など)に対し、「その内容に納得できない」「今は支払い能力がない」といった理由で、正式に『反対の意思』を示す手続きです。これを行うことで、支払督促の効力を一時的に停止させ、通常の訴訟手続きへと移行させることが可能となります。
具体的な手続きの流れ
1.支払督促に同封されている「異議申立書」の用紙を使うか、裁判所のホームページから書式をダウンロードします。
2.以下の項目を記載してください。
・事件番号
・当事者(あなたと債権者)の氏名・住所
・異議の理由(例:「一括返済は困難であり、分割払いを希望します」「債務の存在に争いがあります」など)
・申立て年月日
・申立人(あなた)の署名・押印
3.異議の理由については、詳細な反論は必要ありません。「一括返済は難しいので、分割払いで解決したい」「現在の収入状況では支払いが困難です」といった簡潔な記載で十分に効力を持ちます。
4.最も重要なのは、14日以内に裁判所に確実に到達させることです。郵送の場合は消印日が基準となるため、期限が迫っている場合は直接裁判所に持参することをおすすめします。
異議申立てが受理されると、事件は通常の訴訟手続きに移行し、債権者との和解交渉の機会が得られるでしょう。この段階で、月々の返済額や返済期間について、条件を見直すことがになります。ただし、異議申立て後の訴訟対応は専門的な法的知識を要するため、早めに弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
【訴状・呼出状】答弁書提出と和解交渉の進め方
訴状と呼出状が届く状況とは、債権者があなたに対し、正式な民事訴訟を起こしたことを意味します。あなたは指定された第1回口頭弁論期日までに『答弁書』を提出する必要があります。通常、この期限は訴状が届いてから約1ヶ月程度の余裕がありますが、決して油断はできません。
答弁書とは
答弁書とは、裁判所に対し、債権者の主張(訴状の内容)に対するあなたの反論や事情を伝えるための重要な書面です。
答弁書提出時のポイント
「請求原因に対する認否」の項目では、債権者が主張する借入金額や契約内容、延滞状況などについて、事実関係に応じて「認める」「否認する」「不知(知らない)」のいずれかで回答します。たとえ借入れの事実を完全に否認できない場合でも、「借入れの事実は認めますが、現在の生活状況では一括返済は不可能です」といった形で、あなたの支払い能力の限界を明確に伝えることが重要です。
「反論・主張」の欄には、現在の収入・支出状況、家族構成、病気や失業などの特別な事情を具体的に記載しましょう。例えば、「月収手取り18万円、家賃6万円、生活費8万円、子どもの学費3万円のため、月々2万円程度の分割返済が限界です」のように、数字を用いて客観的に示すことで、裁判官に対してより説得力のある主張が可能です。
和解交渉の進め方
第1回口頭弁論では、多くの場合、裁判官から和解の勧告が行われます。和解手続きは、あなたと債権者の双方が歩み寄って現実的な解決策を見つける貴重な機会です。債権者側も、長期にわたる訴訟を続けるよりも、確実に借金を回収できる方法を優先する傾向があります。そのため、誠実な姿勢で分割払いの提案を行えば、合意に至る可能性は十分に期待できるでしょう。
和解交渉では、月々の返済額だけでなく、遅延損害金の減額や免除、返済開始時期の調整なども話し合うことができます。ただし、提案する返済計画は、あなたが現実的に継続できるものでなければなりません。無理な約束をして再び滞納してしまえば、今度は和解調書に基づいた強制執行があなたを待っています。
【強制執行予告】最後の48時間でできる対処法
強制執行予告通知や債権差押命令が届く段階になると、まさに「最後の砦」と呼べる状況です。この時点で給与差し押さえまでの猶予は、通常わずか48時間から1週間程度しか残されていません。しかし、まだ諦める必要はありません。この緊急事態に、まだ打てる手は存在します。
最後にできる対処法
・債務整理手続きの緊急申立て
最も効果的なのは、任意整理、個人再生、自己破産などの債務整理手続きを緊急で申し立てることです。弁護士が債権者に受任通知を送付することで、強制執行の一時停止を求めることができます。多くの債権者は、債務整理手続きが開始されることを知れば、一定期間執行を待ってくれる傾向にあります。これは、強制執行を続けるよりも、債務整理の中で計画的に回収を図る方が、結果として多くの金額を回収できる可能性が高いと判断するためです。
・緊急の資金調達による一部弁済
親族からの借入れ、生命保険の契約者貸付、退職金の前払い制度などを利用し、債権者との交渉材料となる金額を準備することも選択肢の一つです。借入金全額を支払う必要はありません。債権者に対し、「返済の意思と能力がある」ことを示すことが重要です。例えば、100万円の債務に対し20万円程度を支払い、残額について現実的な分割払い計画を提示すれば、交渉のテーブルについてもらえる可能性があります。
・勤務先への事前相談
給与差し押さえが実行されると、勤務先にも通知が送られます。職場での立場が悪化するのではないか、と心配されるかもしれません。事前に人事部門や信頼できる上司に事情を説明し、理解を求めておくことで、精神的な負担を軽減できるでしょう。場合によっては、会社から低利での貸付制度を紹介してもらえる可能性も考えられます。
この段階になると、まさに時間との戦いとなります。複数の対処法を同時進行で進めることが非常に重要です。弁護士への相談、資金調達の検討、勤務先への相談を並行して行い、あなたの状況に最も現実的で効果的な方法を選択してください。一人で抱え込まず、家族や信頼できる友人にも状況を共有し、協力を求めることも大切です。
法的手続きには複雑な規則と厳格な期限が伴うため、一般の方が単独で完璧に対応することは困難です。弁護士や司法書士といった専門家であれば、あなたの具体的な状況に応じた最適な解決策を提案し、債権者との交渉も代行してくれます。多くの法律事務所で初回相談を無料で受け付けています。まずは早急に専門家に相談することをおすすめします。
差し押さえ実行後に解除・軽減する方法
差し押さえがすでに実行されてしまった後でも、『もう打つ手はない』と諦める必要はありません。実は、状況を改善するための方法はいくつか残されています。ここでは、差し押さえられた財産の解除手続きから、給与や預金の禁止範囲を活用した軽減策、そして今後の生活資金確保の方法まで、具体的な手段を詳しく見ていきましょう。
すでに差し押さえされた財産の解除手続き
残念ながらすでに差し押さえが実行されてしまった財産であっても、一定の条件下では解除手続きが可能です。この手続きは法的にも複雑なものですが、適切に進めることであなたの財産を取り戻せる可能性があります。
債権者との「取下げの合意」による解除
最も現実的な方法といえます。債権者とあなたが合意に達した場合、債権者が自ら差し押さえを取り下げてくれます。この場合、債務の一部または全額を弁済することや、将来の返済計画への合意、担保の提供などの条件が設定されることが一般的です。例えば、100万円の債務に対して70万円を一括返済することで、差し押さえを解除してもらうといった交渉が成立するケースもあります。
「供託」による解除
供託とは、差し押さえられた債権額に相当する金額を法務局に預けることで、差し押さえの効力を一時的に停止させる制度です。供託されたお金は、後に債権者への返済に充てられるか、あなたに返還されることになります。特に給与差し押さえが長期化しそうな場合など、生活の安定を図るために活用される方法です。
「執行異議の申立て」
差し押さえ手続き自体に法的なミスや問題がある場合に利用できます。例えば、債務名義に書かれた金額と実際の債務額に違いがある場合、時効が成立している場合、あるいはすでに返済済みの債務について差し押さえが行われた場合などがこれに該当します。この申立てが認められれば、差し押さえ自体が取り消されることになります。
これらの手続きを進めるには、関連書類の収集、法的要件の確認、申立書面の作成など、専門的な知識が不可欠です。また、成功率を高めるには、差し押さえの実行後、できるだけ早期に着手する必要があります。
給与差し押さえの禁止範囲
給与の差し押さえについては、禁止範囲が法律で明確に定められています。これは、あなたの最低限の生活を保障するための重要な制度です。
差し押さえ禁止の金額
原則として、手取り給与額の4分の3までは差し押さえが禁止されています。例えば、手取り月収が20万円の場合、15万円までは保護され、実際に差し押さえられるのは最大で5万円です。ただし、この計算には例外があり、手取り額が33万円を超える場合は、33万円を超える部分については全額が差し押さえの対象となり得ます。
養育費や婚姻費用の債権
養育費や婚姻費用といった特別な債権による差し押さえの場合、その制限はより厳しくなります。手取り給与の2分の1までしか差し押さえることができません。手取り20万円であれば、10万円までは保護され、差し押さえられるのは最大10万円となるでしょう。
税金や社会保険料の滞納
税金や社会保険料の滞納による差し押さえは、国税徴収法に基づき、民事執行とは異なる基準が適用されます。生活費相当額(給与所得者の場合は月額10万円程度)を除いた部分について差し押さえが可能とされますが、具体的な金額はあなたの家族構成や生活状況を考慮して決定されることになります。
これらの禁止範囲を超えた差し押さえが行われた場合、あなたは「差押禁止債権の範囲変更の申立て」を行うことで、その是正を求めることができます。生活状況の変化、扶養家族の増加、医療費の負担増加などを理由に、差し押さえ金額の減額を求めることが可能です。例えば、家族の介護が必要になった場合や、子どもの学費の負担が増えた場合などは、具体的な資料を提出して生活の困窮状況を説明することで、差し押さえ額の軽減が認められるケースもあります。
預金・口座凍結からの回復と資金を確保する方法
預金口座が差し押さえられると、たちまち日常生活に必要な資金の確保が難しくなることでしょう。しかし、ご安心ください。適切な対応を取ることで、生活資金を確保し、状況を改善する方法はあります。
生活費相当額の返還請求
もし差し押さえられた預金の中に、給与振込直後の生活費相当額が含まれている場合、その部分については返還を求めることができる可能性があります。給与の差し押さえ禁止範囲と同様に、生活に必要不可欠な資金は保護されるべきとされています。この請求を行う際は、家計収支の詳細な説明資料や、差し押さえられた預金が『給与振込』『生活費』『貯蓄』のいずれであるかを明確に示すことが重要です。
別口座での資金確保
差し押さえは特定の口座に対して行われるため、他の金融機関に新しい口座を開設することで、今後の収入や生活費を保護できる可能性があります。ただし、同じ名義の他の口座についても追加で差し押さえられるリスクがないとは限りません。できるだけ早期に、根本的な解決策を講じることが必要でしょう。
家族名義口座の活用
配偶者や成人した子どもの口座を一時的に活用することは、当座の資金繰りとして考えられます。しかし、これは債務者本人の財産隠しと判断される可能性もゼロではありません。透明性を保ち、あくまでも一時的な生活費確保の手段として位置付けることが大切です。
現金での給与受取り交渉
勤務先に事情を説明し、一時的に現金で給与を支給してもらうよう依頼することも有効な手段の一つです。振込による差し押さえを回避できる場合があります。多くの企業は従業員の生活困窮に理解を示し、可能な範囲で協力してくれることでしょう。
一時的な資金確保だけでは根本的な解決にはならず、継続的な差し押さえのリスクが残ってしまいます。これらの対応と並行し、問題の根本解決のためには債務整理手続きの検討が不可欠です。
第三者異議申立て|配偶者名義の財産を保護する方法
もし給与差し押さえの影響が、配偶者名義の財産にまで及んでしまった場合、『第三者異議申立て』という法的な手続きを活用することで、適切にその財産を保護できます。この制度を正しく理解し、活用することは、ご家族の生活基盤を守る上で非常に重要となるでしょう。
第三者異議申立てが必要となる具体的なケース
最もよくあるのは、夫婦共有名義の預金口座が差し押さえられてしまうケースです。例えば、夫の借金による差し押さえで、夫婦共有名義の口座全体が凍結されてしまった場合、妻の持分については第三者異議申立てにより保護を求めることが可能です。
実際の事例では、共働きの夫婦の共有口座に妻の給与も振り込まれていたにもかかわらず、夫の債務により全額が差し押さえ対象となったことがありました。しかし、妻が給与明細や家計簿を証拠として第三者異議申立てを行った結果、妻の持分に相当する金額の保護が認められています。
また、配偶者名義で購入した生活必需品(家電製品や家具など)が差し押さえられそうになった場合も、適切な証拠があれば異議申立てにより保護できる可能性があります。
申立てに必要な証拠と手続きの流れ
第三者異議申立てを成功させるためには、その財産が配偶者固有のものであることを客観的に証明する必要があります。預金の場合は、配偶者の給与明細、振込記録、家計簿などが重要な証拠となるでしょう。
1.まず、管轄の地方裁判所に『第三者異議申立書』を提出します。
2.申立書には、異議の対象となる財産の詳細、申立人(配偶者)との関係、財産の取得経緯などを明確に記載してください。
3.申立て後、裁判所は債権者と申立人双方の主張を聞いた上で判断を下します。この過程で、配偶者の財産であることを示す追加の証拠提出が求められる場合もあります。
第三者異議申立ては、法的に複雑な手続きです。特に、夫婦間の財産関係が複雑な場合や、共有財産と個人財産の区別が不明確な場合は、司法書士や弁護士といった専門家のサポートを受けることが不可欠といえます。
任意整理以外の選択肢|他の債務整理の方法による対策
任意整理では差し押さえを直接止めることは難しいでしょう。しかし、個人再生や自己破産といった裁判所を通じた債務整理の手続きであれば、申立てと同時に「中止命令」や「破産手続開始決定」によって差し押さえを停止させることが可能です。
これらの手続きは法的な拘束力が非常に強く、債権者は裁判所の決定に従わざるを得ません。ただし、それぞれに異なる条件や特徴があるため、あなたの現在の状況に最も適した方法を選ぶことが重要です。
個人再生で差し押さえを止める方法|中止命令の条件と手続き
個人再生とは、借金を大幅に減額(通常5分の1程度)し、残りを約3年間で分割返済していく手続きです。この手続きの最大の特徴は、住宅ローン特別条項を利用することで、大切な自宅を手放すことなく債務整理ができる点にあります。
差し押さえを止める「中止命令」
個人再生の申立てと同時に、差し押さえを止めるための『中止命令』を裁判所に申請します。裁判所が「再生手続きを進める上で、この差し押さえが障害になる」と判断すれば、即座に中止命令が出されるでしょう。給与差し押さえが続けば、あなたの生活が破綻し、再生計画の実行が困難になることは明らかです。そのため、多くのケースで中止命令が認められています。
個人再生を利用するための主な条件
・借金総額が5,000万円以下であること
・継続的に安定した収入が見込めること(会社員の場合、手取り月収20万円程度あれば十分に検討可能です)
・住宅ローンがある場合は、住宅ローン以外の借金が住宅の評価額の1.5倍以下であること
手続きの流れと期間・費用
1.弁護士に依頼後、必要書類を準備し、裁判所に申立てを行います。
2.申立てから中止命令までは、通常1〜2週間程度です。
3.その後、再生委員との面談、債権調査、再生計画案の作成と続き、手続き全体で6〜8ヶ月程度の期間を要します。
4.費用は、弁護士費用が40〜60万円、裁判所費用が3〜5万円程度が目安となるでしょう。
自己破産による差し押さえ停止|中止命令申立ての流れと注意点
自己破産とは、裁判所に「支払不能」状態であることを認めてもらい、借金を免除(免責)してもらう手続きです。手続きの進行に伴い、給与などの差押えについても停止させることができます。
差押えの停止には、「破産手続開始決定」が出された後、その決定書等をもとに執行裁判所へ「執行中止の上申書」を提出する流れが必要になります。これにより差押えが「中止」となり、債権者や会社(第三債務者)にも通知されます。
個人再生の場合の「再生手続開始決定の写し」に基づく中止命令とはやや手続き経路が異なりますが、実務的には自己破産でも執行裁判所に申請が必要です。申立てを行い、通常1~2週間で「破産手続開始決定」が出され、その後に「執行中止の上申」を迅速に行うことが重要です。もし緊急性が高ければ、弁護士を通じて保全処分等の追加申請も検討しましょう。
最大のメリットは、借金が原則としてゼロになることです。給与差押え状態にある多重債務者にとっては抜本的な解決策となります。注意点として、20万円を超える価値の財産(車、貴金属、有価証券等)は原則処分対象となるほか、手続期間中は警備員や宅建士等の資格制限も課されます。ただし、一般の会社員であれば勤務継続や秘密保持が可能な場合も多いです。
手続き費用は、弁護士費用30~50万円、裁判所費用2~3万円ほどが相場です。「同時廃止事件」であれば手続き完了まで3~4ヶ月、「管財事件」でも6~8ヶ月程度が一般的です。
弁護士・司法書士選びの基準と相談タイミング
専門家を選ぶ際に最も重要なのは、債務整理案件の実績と経験です。一般的な法律業務とは異なり、債務整理は債権者との交渉力や、手続きの迅速性が結果を大きく左右します。年間100件以上の債務整理案件を扱っている事務所であれば、豊富な経験に基づいた適切なアドバイスが期待できるでしょう。
専門家選びの主な基準
・債務整理の実績と経験が豊富である:特に交渉力や手続きの迅速性を重視しましょう。
・初回相談が無料:経済的な負担を気にせず、複数の専門家の意見を聞き比べるためにも重要です。
・対応が迅速:債務整理は時間との勝負となることも多いため、電話やメールへの返答が24時間以内など、対応が早い事務所を選ぶことをおすすめします。
『もう少し様子を見てから』と相談を先延ばしにするほど、あなたの選択肢は狭まってしまいます。督促状が届いた段階、ましてや裁判所からの通知が来た時点では、既に一刻の猶予もありません。「返済が厳しい」と感じたその瞬間こそが、専門家への相談を検討すべき最適なタイミングなのです。
まとめ
給与などの差し押さえという状況に直面したとき、「もう手遅れだ」と深い絶望感を抱くかもしれません。しかし、たとえ差し押さえが始まってしまった後であっても、あなたの状況を改善するための選択肢は、まだ残されています。
このような複雑でデリケートな状況だからこそ、債務整理に詳しい弁護士や司法書士への相談が不可欠です。専門家は、法的な知識と豊富な経験に基づき、あなたの状況を詳しく分析し、最も現実的で効果的な解決策を提案してくれます。相談することで、今まで見えなかった選択肢が明らかになったり、手続きの見通しが具体的に分かったりすることで、精神的な負担も大きく軽減されるはずです。
差し押さえが執行される段階では、時間との戦いになり、一刻を争う事態になることも否定できません。このような状況を避けるために、一人で悩み続けるよりも、早い段階で専門家にご相談されることをおすすめします。